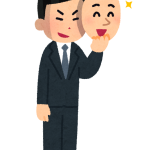こんな人におすすめの記事
- 賃貸と持ち家、どっちが得か知りたい
- FIRE後に住む場所は賃貸・持ち家どちらが有利か知りたい
FIRE(アーリーリタイア)を目指しているのなら、
賃貸を選択する方が有利
です。
なぜなら、数千万円という資金が株式のような収益を生むものではなく、
持ち家という一切収益を生まないもの
に代わってしまうから。
例えば、3,000万円あって株式を買って利回り4%なら、毎年120万円の利益を生みます。
一方、戸建て住宅を買ったら、この120万円/年は得られず、不動産購入がFIRE達成の足かせとなるのです。
しかし、

FIREするまでは賃貸有利なのは分かりました。
では、FIREした後はどっちを選択すればいいのかな?
といった疑問が出てきます。
結論として、
・基本的には、FIREを目指す段階と変わらず「賃貸」が有利
・しかし、FIREすると借りられなくなるリスクがある
条件次第では「持ち家」も選択肢に
となります。
この記事では、賃貸・持ち家それぞれにどういったメリット・デメリットがあるか解説していきます。
自分にとってどちらを選択するのがベターか考えていきましょう。
本記事の参考書籍 FIRE 最強の早期リタイア術

就職先や投資先の選び方まで、これ1冊を読めば、FIRE達成までのロードマップが記されております。
この記事では、賃貸か購入のいずれが有利となるかの指標として、主にこの本に記されている「150の法則」を引用しております。
尚、一読して個人的に印象に残った言葉は、
銀行員こそ本物の銀行強盗
です(笑)
こちらの書籍にプラスして、私の宅建士歴15年の経験を踏まえて解説していきます。
FIREを目指すなら、大多数の人は賃貸に住み続けるべき理由

冒頭で述べたように、FIREを目指す人は基本賃貸有利です。
理由として、
①物件購入には数千万円のまとまった資金が必要であること
②ローン契約時の収支状況が、いつまでも続くとは限らない
が挙げられます。
物件購入には数千万円のまとまった資金が必要であること
まず、1つ目の理由は冒頭で述べたとおり、投資に回すお金が少なくなるため、必然FIRE達成の足かせとなります。
3,000万円の物件をキャッシュで購入したら、あとは残りの金額で資産運用しなければなりません。
もし3,000万円を4%で運用していたら、得られる年間利益は100万円を超えます。
20年で物件購入していないのと
2,000万円もの差
が付くわけですから、非常に大きな差と言えるでしょう。
ローン契約時の収支状況が、いつまでも続くとは限らない
また、35年も先、自分と回りの家族や社会情勢がどうなっていることか・・・全く予想できませんよね?
・解雇・倒産・役職定年で収入激減
・低金利時代が終焉し、金利上昇
・親の介護で新たな出費が発生
などなど、ローンを組んだ時点と状況が変わることは容易に予測できます。
もし完済前に上記のようなことがあると、返済不能に陥り最悪売却しなければならない事態もあり得ます。
まだ売却してローンが消えればいい方で、もし希望の価格で売れないと
売却してもローンが残る
という最悪の事態に!?
収入減、支出増の恐れは年齢を重ねると出てくる問題であるため、
今の収支状況だけをベース安易にローンを組まない
ことが重要です。
このリスクの例は、正直不動産にて「ペアローン」のリスクが取り上げられましたね。
-

-
ペアローンの最大デメリットは離婚!? 正直不動産3話を視聴した現役不動産営業の解説
スポンサーリンク この記事は、2007年から主に不動産業界にいる私が、 正直不動産(3話) を視聴しドラマの中で出てきた専門用語を解説しております。 早いもので、もう3回目にもなるのですね さて最初に ...
続きを見る
150の法則:月々の返済に1.5を掛けた数字が現在の賃料を下回るときは持ち家有利?

では、どういったケースで、物件購入した方が賃貸より有利となるのでしょうか?
参考書籍を読んでみると、購入が賃貸より有利になるのは、
150の法則:月々の返済金に150%(1.5)を掛けた数字が、今の賃料より安いとき
と記されております。
分かりやすく、具体的な数字を入れてみましょう。
例:家賃10万円 物件購入後の月々の返済額8万円 の場合
※月々の支払いにフォーカスするため、ここでは一旦物件の購入価格は考慮しません。
買ったときの値段と売ったときの値段は同じとします。
これだけ見ると2万円月々の負担が減っているため、買った方が得に見えますね?
しかし、かかる費用は
ローンの返済だけではない
ことを忘れてはいけません。
賃貸では支払い不要な以下の3項目が、月々ないし年間かかってきます。
固定資産税・都市計画税
土地・建物は所有しているだけで、毎年税金がかかります。
たとえ返済が終了しても、物件の所有者である限り税金がかかるため、負担が0になることはありません。
よく土地の価格が上がると喜ぶ人がおりますが、
評価額が上がると税金も高くなる
ため喜んでばかりはいられませんよ。
東京都23区内などの好立地は、当然評価額が高いですが税金も高い💦
そのため、利益を生まない物件や土地を所有していると、多額の税金という名のコストが掛かってしまうのです。
設備の故障・不具合の修理費・リフォーム費用
物件も設備も日に日に劣化します。
エアコンや給湯器は10~15年くらいで交換が必要です。
また、壁紙・床・建具なども経年劣化し、建築後20~30年経てば大規模なリフォームが必要となります。
これらの費用は、賃貸なら
原則オーナー負担
です。
しかし、持ち家の場合オーナーは自分自身のため、これらの費用は当然自身で負担しなければなりません。
メンテナンス費は、生活費とは別に積立てておく必要があるのです。
管理費・修繕積立金
マンションの場合のみとなりますが、管理費・修繕積立金が合算で3~4万円/月かかります。
他にも駐車場を借りたり、コンシェルジュサービスを利用したりすると、さらに出費はかさみます。
また、修繕積立金は最初はあまり補修する箇所もなく低く設定される傾向です。
しかし、築年数を重ねると、
- 外壁の大規模修繕
- 新規設備の導入
といったことが必要となり、修繕積立金は将来ほぼ上がっていきます。
尚、戸数の多いマンションを買うことで、将来修繕積立金が大幅に上がるリスクを軽減できます。
ただし、戸数が多いからといって絶対に上がらないとは限らないため、そこは頭に入れておきましょう。
月々の返済額×1.5<賃料となれば持ち家有利であるが・・・
150の法則は、
150の法則の前提条件
- 1つの物件に居住する平均年数(アメリカでは9年)
- その間に発生する維持費(税金や設備の補修費など)
が概ね返済額の1.5倍となることからできた計算式です。
上記例を計算式にあてはめてみると、
8万円 × 1.5 = 12万円 > 家賃10万円
となります。
よって、上記の例だと賃貸有利となるのです。
もし、月々の返済が6万円で済めば計算結果は9万円となり、購入有利となります。
6万円 × 1.5 = 9万円 < 家賃10万円
ただし、参考書籍はアメリカ基準のため、日本の場合はさらに厳しい数字で算出しなければなりません。
なぜなら、
アメリカ → 物件価値は中古になっても上がっていく
日本 → 物件価値は築年数とともに下がっていく
といった違いがあるから。
結局のところ日本の場合、ずっと賃貸に住み続ける方が持ち家より金銭的に有利となる可能性が高いと言わざるを得ませんね・・・
FIRE後の賃貸のデメリット

前述のとおり、お金の面だけにフォーカスすれば、日本に住み続ける限りまず賃貸の方が有利です。
しかし、賃貸にも無視できないレベルのデメリットがあることを忘れてはいけません。
それが以下の3点です。
・借りられなくリスク
・ 賃貸契約上さまざまな制約がある
・エリアや家族構成によっては、むしろ賃貸の方が割高に
借りられなくなるリスク
前提として、FIRE後は一切働かないことを想定しております。
つまり、世間的に見ればいくら資産を持っていようとも、
リタイアしたら年収0の無職扱い
そのため、物件を借りようとしても、オーナー側が貸してくれません。
さらに、これは本来あってはならないことではありますが、
高齢を理由に入居を断られるケース
も多々あります。
※本記事執筆の前日も、高齢を理由にオーナーから入居を断られました。

人口減っているし、別に年を取っても貸してくれるところはあるでしょ?
と安易に考えないで下さい。
普段から不動産賃貸の現場で働いている感覚では、しばらくオーナー側が主導権を握る状況が続くと考えております。
FIRE後は間違いなく社会的信用が下がることは、覚悟しなければなりません。
賃貸契約上さまざまな制約がある
最低限の設備があれば住めるだけでOKという人は問題ございません。
しかし、いろいろとやりたいことがある人にとって、賃貸は制約が多いことがデメリットとなります。
基本的なところでいくと、ペットの飼育
これまでの経験上、体感で
賃貸物件の9割くらいはペット不可
複数頭の飼育や大型犬、猫となるとさらに物件数は限られます。
将来猫や犬を飼いたい人は賃貸ではなかなかいい物件に巡り合えないため、物件を購入せざるを得ないでしょう。
その他にも、
ポイント
- 自宅で楽器の演奏をしたい
- DIYや内装を自由にリフォームしたい
といった意向は、賃貸物件ではまず叶いません。
上記のような意向が本人または同居家族の中にあるようなら、
限られた賃貸物件の中から選ぶ
より、
いっそ持ち家を購入する
といった選択をするのもありかと存じます。
エリアや家族構成によっては、むしろ賃貸の方が割高に
例えば、子供が4人いる6人家族であったなら、3LDKの物件では広さや部屋数が足りません。
そうなると、賃貸マンションの選択肢はほぼなく、必然4LDK以上の戸建てを探す必要があります。
しかし、賃貸の戸建ては少なく、しかも築年数が古いものばかり・・・
にも関わらず、東京都内近郊では
100㎡あれば賃料25万円以上
であることはざら💦
都内で月25万円もの家賃を支払うのなら、少し郊外で3000~4000万円台の戸建てを買った方が住宅コストは安く済みます。
25万円/月の賃料が年利5%だったと仮定し「収益還元法」で物件価値を計算すると、
25万(月額賃料) × 12(ヶ月) ÷ 5% = 6,000万円
となり、6,000万円の持ち家を買ったのと同義となるからです。
収益還元法とは? 収益還元法 - Wikipedia
ウィキペディア
・ファミリーで3LDK以上は必要
・東京および近県3県の都心に近いエリア
この両条件に当てはまる方は、十分持ち家を選択肢に入れてもいいと考えられますね。
東京都以外でも、賃貸では基本広くなれば広くなる程、物件は少なくなります。
経験上、3LDK以上はマンション・戸建て関わらず、金銭面からも持ち家を検討してよいかと存じます。
よって、一概に全員には当てはまらないかと存じますが、
・単身者or子供のいない夫婦 → 2LDKまでの賃貸
・子供のいるファミリー → 2LDKまでの賃貸 or 3LDK以上の持ち家
を目安に賃貸か持ち家かを判断するのがベターです。
FIRE後のデメリットを回避する方法

前述のとおり、FIREは世間的には無職とみなされます。
そのため、賃貸物件を借り続ける場合、以下のいずれかで対策を講じる必要があります。
①UR賃貸を借りる
②キャッシュで物件を購入する
③契約者名義を働いている同居者や別の親族にする
④セミリタイアに切り替える
UR賃貸を借りる
私は仕事上で全く関わったことがなく経験談を語れないのが残念ですが、UR物件は
家賃の100倍預貯金があれば無職でも入居ができる
ようです。
100倍と聞くと

5万円の家賃で500万円も貯金が必要なの?
とハードルが高そうに感じますが、そもそもFIREする人がこのくらい資産を持っていないはずがありません。
通常の賃貸では資産はほとんど考慮されず、年収のみで審査します。
一方、URの場合は資産で見てくれるため、FIRE後でも入居できる可能性はあります。
ただし、株式や債券は考慮されないようなので、一時的に現金比率を高めて見せ金を多くし、入居できるようにするのも手です。
キャッシュで物件を購入する
「賃貸に住み続ける」から逸脱する手段ですが、
いっそ購入してしまう
のも手です。
上述のとおり無職では借りられない物件が多いし、さらに加齢とともに審査をクリアするハードルは上がります。
また、単身ならともかく、ファミリーなら家族の意向も無視するわけにいきません。
そこで、物件を購入してしまえば、借りられなくて住むところがない事態は避けられます。
ただし、条件として
キャッシュで買うこと
ローン審査も賃貸の審査同様、無職や高齢であることが理由で通らないからです。
尚、購入すると資産の多くが不動産となるため、運用利回りが低下することには要注意。
購入後に減ってしまった資産から得られる利益でも今後の生活に支障がないか
十二分に計算しましょう。
契約者名義を働いている同居者や別の親族にする
夫婦やファミリーの場合、配偶者が働いているようなら
名義を自分以外にすること
で賃貸物件を借りられる場合があります。
単身者なら、両親や兄弟で働いている方名義で借りるのも手です。
しかし、両親や兄弟など同居者以外での代理契約は、物件によってはできません。
私も仕事上で取扱うことのある某大手メーカーの物件は、入居者が学生の場合を除き代理契約不可
物件によってはこの方法が使えないことを覚えておきましょう。
セミリタイアに切り替える
社会的信用を失わないため、
とりあえず仕事を続けてみる
のも手です。
楽そうな仕事へ転職したり、知人に経営者がいればお手伝いしたりして、一定の給与所得を残しましょう。
いくらお金を持っていることを主張しても、オーナー側は基本年収しか見てくれません。
しかし、少しでも社会に関わり仕事をしていれば、入居申込書の勤務先欄および年収を埋めることができます。
審査の土台には乗せることができるようになるため、必然審査が通る物件は増えてくることでしょう。
まとめ
最後に本記事のまとめです。
・FIREを目指す段階では、賃貸が金銭的に有利
・FIRE後も賃貸が金銭的に有利だが、条件次第では持ち家も検討する価値あり
持ち家のデメリット
・資産の多くを不動産に回すため、資産運用に回せる資金が減少する
・ローン契約時の収支状況が、いつまで続くか分からない
無理したローン契約は、支出減や出費増で支払い不能に陥る可能性あり
賃貸のデメリット
・FIREは無職扱い。加齢もマイナス要因で、借りられなくなるリスクがある
・賃貸契約には、さまざまな制約がある(ペット不可、楽器演奏不可など)
・家族構成・お住まいのエリアによっては、賃料が高くむしろ買った方が安い場合も
FIRE後に賃貸を借りるための方法
・UR賃貸を借りる(預金でも審査してくれるため)
・契約名義を同居者や親名義にする
・いっそ物件を購入する(ローン審査は難しいのでキャッシュ購入限定)
・セミリタイアして社会的信用を維持させる
これまで述べてきたとおり、多くの不動産が基本右肩下がりで価格が下落する日本においては、金銭的には賃貸有利と言わざるを得ません。
しかし、無職であることや高齢であることを理由に、借りられなくなるリスクがあることは事実・・・
そのため、状況によっては物件を購入するのはありと結論づけます。
ただ各人の考え方は尊重されるべきで、いい家に住むことに大きな価値観を持つ人は、本記事の計算式で賃貸有利と判断された物件を購入しても構いません。
人気書籍の
バビロン大富豪の教え
でも「より良き家に住め」と、家は富豪になるために重要であると説かれれております。
賃貸・購入問わず、各々の価値観に合った物件を選んでいきましょう。
あわせて読みたい関連記事