
FP3級の最初の分野、「ライフプランニングと資金計画」
過去の試験で出題が多い箇所をまとめてみました。
尚、この分野で最もつまずきやすい「6つの係数」については、下記記事で詳しく解説しております。
-

-
FP3級最初の難所「6つの係数」を解く裏技とは?
スポンサーリンク こんにちは、TAKASUGIです。 普段からお金についての情報を、ブログやSNSで発信しています。 ただ、株式投資の投資歴は15年とそこそこあれど特段資格や金融系企業への勤務歴はなく ...
続きを見る
ファイナンシャル・プランナーとは?
まず、
FPとは、どんな仕事をするのか?
何ができるのか?やってはいけないのか?
を押さえましょう。
必ず、序盤の〇✖問題に出題されます。
FPが守るべきこと(職業倫理)
①顧客利益の優先
×自己の利益優先で顧客に商品を進める
②守秘義務の遵守
×○○さんが、私のところに相談しに来たよ
③説明義務(アカウンタビリティ)
FPの仕事の範囲と関連法規
仮定の事例の説明、一般的な相談は〇
個別具体的な相談、他士業の独占業務を行うは×
・弁護士法
〇公正証書作成時の証人 相続関連のセミナー
×遺言書の作成 相続財産の分割案
・税理士法
〇一般的な税法の説明 仮定の数値で税計算
×確定申告書の作成 代理で税務申告
・保険業法
〇保険の見直し相談 遺族の必要保証額の計算
×保険の募集 保険契約の締結

公正証書作成時の証人は、推定相続人以外誰でもなれる
難しそうな言葉が並んでいるので、個別具体的と勘違いしないように!
尚、士業の独占業務を無償で行っても違法です。
有償・無償を問わない
ことは、よく覚えておきましょう!
FPの業務アプローチ方法
FPがライフプランニングを行うとき、下記3つのツールを利用します
①ライフイベント表
②キャッシュフロー表
③個人バランスシート

②および③がよく出題される
キャッシュフロー表
・収入は可処分所得を記入
可処分所得=額面の総収入-(所得税+住民税+社会保険料)
簡単に言い換えると手取り
※強制的に引かれない生命保険料は含まない
・変動率がある項目は将来価値を記入
n年後の額=現在の額×(1+変動率)n
例:年収500万円、変動率1%として3年後の想定年収は?
500万円×(1+0.01)3 = 515万円

将来価値の計算は、資産運用の複利計算でも利用します
個人バランスシート
・建物など不動産は時価で計算 ×購入時の価格
・生命保険の価値は解約返戻金額
・純資産=資産-負債

家を5000万円で買ったとしても、今3000万円でしか売れないなら3000万円が正
今亡くなれば1億円下りる生命保険も、今解約して戻るのが100万円なら100万円が正
6つの係数
FP試験最初の難関
6つの係数の名前と意味は覚えない
覚えるのは、必要な数字を抜き出して計算する方法を覚えることです。
※2023年6月11日追記
2023年5月28日の試験で、思いっきり6つの係数の意味を問う問題が出ました・・・さーせん
問題を解くポイント(3つのステップ)
①問題文からおよその係数(何を掛けるか)を推測
②推測した値より大きいか小さいか考える
③表から該当する値を抜き出して計算する

係数は掛け算のこと
割る場合は小数に直しましょう
詳細は下記記事をご確認下さい。
-

-
FP3級最初の難所「6つの係数」を解く裏技とは?
スポンサーリンク こんにちは、TAKASUGIです。 普段からお金についての情報を、ブログやSNSで発信しています。 ただ、株式投資の投資歴は15年とそこそこあれど特段資格や金融系企業への勤務歴はなく ...
続きを見る
人生の3大資金
ライフプランを立てるのに重要なのが、数千万の資金がかかる以下の3つの支出
人生の3大資金
- 教育資金
- 住宅資金
- 老後資金
これらをサポートする商品を覚えていきます。
教育資金
教育ローン・奨学金・学資保険の主に3パターン
教育ローン
日本政策金融公庫が貸し出す
支給要件
・融資限度額は350万円(海外留学等一部450万円)
・保護者が借りて保護者が返す
・返済期間18年 固定金利
・パソコン、国民年金、住宅費にも利用可
・所得制限あり

ローンは学生(子)が返済する
授業料や入学金でしか使えない、といった引っ掛け問題に注意
奨学金
日本学生支援機構等が貸し出す
給付型もあるが、出題されるのは主に貸与型
■支給要件
・学生(子)が借りて学生(子)が返す
・第一種奨学金 → 無利子
第二種奨学金 → 有利子
※ただし、第二種も在学中は無利息
・教育ローンと併用可能

第一種と第二種の利子の有無を逆に覚えないように
第一種を成績1位、第二種を成績2位として
成績1位は優秀だから無利子、2位は成績が劣るから有利子と覚えるのがよい
学資保険
契約者(親)が死亡または高度障害になったら、以降の保険料払い込み免除
免除後も満期金・お祝い金は満額受け取れます
住宅資金
住宅ローンの返済方法は2パターン
元利均等返済・元金均等返済
まず、両方の特徴をざっくり覚えましょう。
元利均等返済
各回の返済額(元金+利息)が一定
最初は利息が多いが、期間経過とともに元金比率が高くなる
一般的に使われている返済方法
下図はよく出てくる元利均等返済のイメージ図
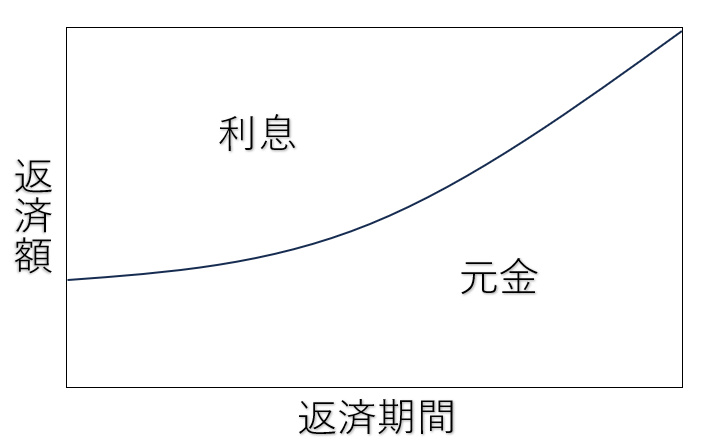
元金均等返済
返済額に占める元金の額が一定
開始時期は支払いが多い
下図が元金均等返済のイメージ図
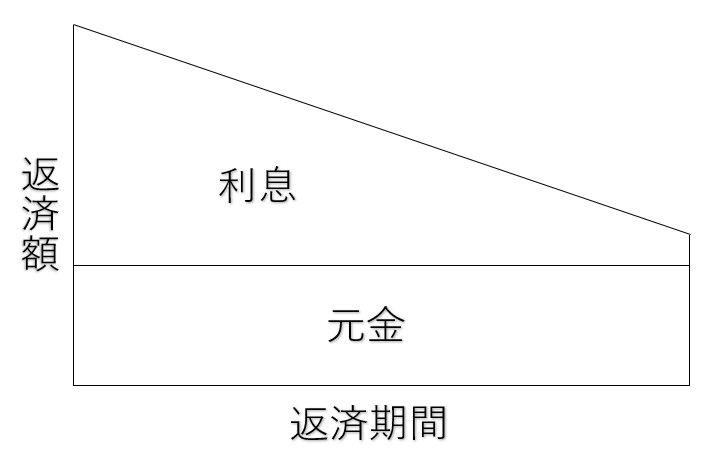
金利や期間が同条件なら、元金均等返済の方が総支払額は少なくなる
また、繰り上げ返済のタイプには
期間短縮型・返済額軽減型
の2種類の返済方法があります。
同一条件なら期間短縮型の方が利息の軽減効果が高くなる

上図の穴埋め問題
2つの返済方法を比較しどちらが総支払額や利息軽減効果があるか
の問題がよく出る傾向です
本編は以上です。
老後資金は後編の公的年金にて解説します。
>>>後編へ続く
